怖い話は好きだろうか?私は大好きだ。
しかし怖い話系のフィクション・ノンフィクションを見ていると、登場人物の圧倒的な若さに気付かされる。
十代の少年少女がメインといってもいい。
なぜ、怖い話と少年少女は相性抜群なのだろうか?
今回は、なるしまゆりの『少年怪奇劇場』を例に、その謎を考察していきたい。
感受性が高いからこそ霊と交信できる
悪魔憑きやポルターガイストが思春期ヒステリーに分類されていた時代があった。
思春期の性衝動や鬱屈が爆発すると、信じられない力を発揮するらしい。
本作の主人公はいずれも十代の少年少女。
恋や友情、進路に悩める中高生だ。
思春期にさしかかった彼らはやり場のない苛立ちやモヤモヤ、抑圧された衝動を抱え込む。
自分は神に選ばれし勇者だとか、世界を救済するヒーローだとか、何かすごい存在かのように思い込んでしまうことをネットスラングで厨二病というが、これは中学2年生が発症しやすいからにほかならない。
大人と子供の過渡期にあり、その気になれば異世界にも行けてしまいそうな想像力のポテンシャルを秘めた彼らが、あの世とこの世のはざまを徘徊する霊たちと交信できてもおかしくはない。
極論、少年少女と霊は同じなのだ。
片や大人と子供のはざまで身体と心が揺れ動き、片やあの世とこの世のはざまでうろうろし、どちらにも居場所がない不安定な存在。
ある意味で同類だからこそ、少年少女と幽霊は波長が合ってしまうのだった。
恐怖体験が成長のトリガーに
少年少女は冒険を経て成長するのが物語の様式美だ。
これは怖い話でも同様で、彼らは恐怖を乗り越えて成長する。
本作の登場人物たちは身も凍る恐怖体験を通し、ある者は新しい友人を得、ある者はいとこと新しい関係に踏み出す。
恐怖が子どもたちに成長を促した、といえなくもない。
いわゆるショック療法だ。
親や教師をはじめとするまわりの大人に頼らず、自力で恐怖を乗り越えることによってアイデンティティを確立する。
大前提として大人はオカルトに懐疑的で、追い詰められた彼らが相談したところでまともに取り合ってもらえないのがオチ。
だからこそ、自分の知恵と勇気で怪異に挑むお膳立てができる。
ただ怖いだけで終わらない、未来への可能性
『少年怪奇劇場』の収録作はどれも余韻を持たせる終わり方をしている。
まだ道半ばの少年少女たちの未来を仄めかすような、続きは読者の想像に委ねるラストなのだ。
彼らの人生はこれからも続いていく。
大人になれば怪異の事を忘れてしまうかもしれないし、一生忘れないかもしれない。
十代の少年少女がホラーの主人公に据えられやすいのは、決着を未来に先送りできるからだ。
万一怪異に負けても絶望するなかれ。
君たちはまだまだ成長途中、リベンジのチャンスはこの先いくらでもある。
仲間の仇をとるため、雪辱をすすぐため、今度こそ引導を渡すため。
動機は様々だろうが、幽霊にいいようにされていた子どもが大人になって、あの頃たちうちできなかった脅威と対決する展開は実にエモい。
大人が過去を振り返る演出もしみじみ感傷をかきたてる。
社会に出て家族を持ち、自立した大人の視点で見直して初めて気付く真実など、少年少女が主人公の場合は一気に歳月を飛ばす事でいくらでもおいしいネタを仕込めるのだ。
幽霊とノスタルジーは相性がいい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
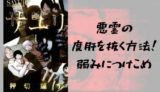 悪霊の度肝を抜く方法!弱みにつけこめ
悪霊の度肝を抜く方法!弱みにつけこめ
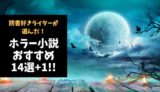
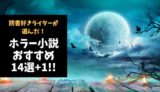
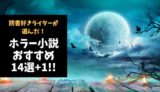
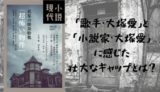
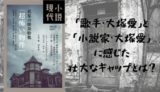
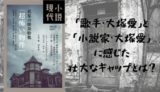
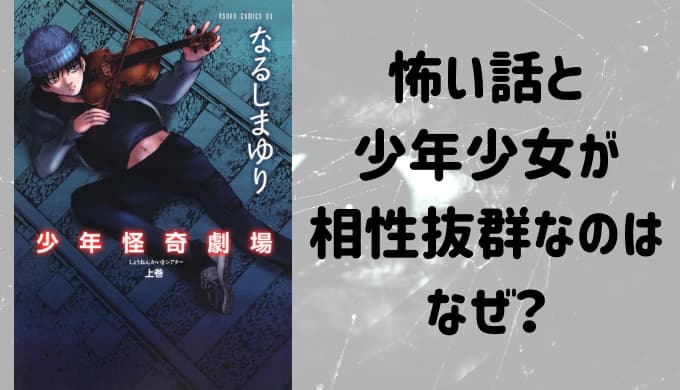


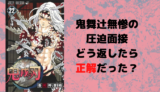
書き手にコメントを届ける