花魁の語源は禿(花魁の世話役の童女)の口癖、「おいらん姐さん」らしい。
即ち、「おいらの姐さんすげえだろ、芸達者でべっぴんだろ!」という自慢に端を発しているそうな。
そうなのだ、花魁はすごいのだ。
花魁道中こそ華やかだが、そこは金で買われる遊女。
女の苦しみ哀しみを味わい尽くし、とことん不幸を舐めたからこそ、したたかに生き抜く知恵を磨き上げた花魁に人生相談をしたら、意外と良いアドバイスをもらえるのではなかろうか。
今回は漫画『あおのたつき』から、遊女の悩みを見ていきたい。
夫の尻拭いは当たり前?借金を返すために売られる女房
本作の主人公は冥途のお稲荷さんに迷い込んだ花魁・あお。
冥途では生前の未練や欲望が姿に反映されるのだが、彼女は何故か子供の姿をしている。
おまけに冥途にも現世と同じ花街があり、バケモノたちで賑わっているのだった。
本作は基本一話完結で、あおのもとを訪れる死者たちが悩みを語っていくのだが、その中に「夫に売られた遊女」がいた。
夫が博打でこしらえた借金を返す為、子供がいたにもかかわらず、「んじゃコイツやるよ」と鬼姑に売っ払われたのだ。
酷い話だが、女を風俗に沈めるヒモや、ダメ男に貢いで尽くす現代の女性たちとさして事情は変わらない。
江戸時代は特に男尊女卑の風潮が強く、「嫁いで3年子なきは去れ」と言われ、子供ができなければ石女(うまずめ)と罵られた。産まず女とかけた残酷な駄洒落である。
たとえ旦那の方に原因があろうとそんな発想すら許されず、すべて女のせいにされたのだから胸糞悪い。
石女の蔑称からも明らかなとおり、姑や旦那は嫁を自分たちの都合でひょいとどかせる漬物石程度にしか思っておらず、遊郭に売っ払ったところでまるで心を痛めない。
花街の遊女は幼い頃に買われるのが大半なので、人妻となると肩身が狭く、年増だの何だのと客や同朋に疎んじられてさんざんだ。
旦那の尻拭いも女房の務め、だからこそ吉原には泣く泣く子供を手放し遊郭に来る人妻が後を絶たないのだった。
子を産めるのは高級遊女だけ!「鬼追い」の実態とは
本作には子供を欲しがる遊女も登場する。
しかし、吉原で子供を産むのが許されるのは部屋持ちの高級遊女だけ。はっきり格付けされているのだ。
江戸時代なので避妊の知識もお粗末なもので、遊女が望まぬ妊娠をすることはよくあった。
遊女が孕むと「鬼追い」が行われた。これは毒のあるほおずきの根を膣に突っこみ、子供を堕胎する方法だ。
ほおずきの根を煎じて飲むなど比較的穏便な方法もあったが、それでも流れない時は箸で突き刺し、無理矢理かきだしたというのだから恐ろしい。
遊郭にとって遊女の胎児は鬼子、厄介者。
孕んでしまえば客をとれず女も店も干上がり、産んだところで養えないとあれば流産するしかない。
ただでさえ莫大な借金に喘いでいるのに、子供なんていたら年季が伸びるだけ。
故に子殺しを鬼追いと称したわけだが、堕胎の罪悪感を軽減する詭弁と思えば胸が痛む。
子供を産み育てるのが女の幸せというのはやや時代錯誤な価値観だが、廓に縛り付けられた遊女だからこそ、叶わない夢や手の届かない幸せに憧れる気持ちはよくわかる。
遊女上がりは三十路近くで住み込みの遣り手婆に!
吉原の遊女はごく幼い頃に遊郭に引き取られ、厳しい躾を受ける。
「ありんす」と語尾に付ける廓言葉が定着したのは、日本中の器量よしが吉原に集められた為、田舎訛を矯正する必要が出たせいだ。
あお自身も飢饉の寒村から、人買いに連れられて吉原にやってきた身の上だ。
新参の遊女や禿の躾を担当するのが遣り手婆である。
遣り手婆は遊女が客と同衾する郭の二階を取り仕切る、郭になくてはならない存在だが、とにかく口うるさく、時に折檻も加えることから、遊女たちには煙たがられてもいる。
早い話、郭の憎まれ役が遣り手婆だ。
しかし彼女たちとて最初から婆だったわけではない、遣り手婆の大半は年老いた遊女上がりなのだ。
物心付いた頃から遊郭で育ち、花街の空気にどっぷり浸かりきった遊女は、仮に年季が明けても市井に馴染めない。
大前提として年季が明ける頃には三十路近くになっており、世間を知らず手に職もない遊女上がりが、食べていくのは大変なのだ。
運よく金持ちに身請けしてもらえれば悠々自適に暮らせるが、せっかく年季が明けても他に行くあてがない遊女上がりは郭に戻るしかなく、住み込みの遣り手婆となる。
そして小娘の頃に叩きこまれた郭の作法や躾、あるいは折檻の痛みを、若い子たちに教え込む。
遣り手婆なら遊女の気持ちがよくわかるし、締め付けの緩急や折檻の匙加減を心得ているというわけだ。
生きるも地獄、死ぬも地獄。花街には女の一生が詰まっている。
出典:amazon.co.jp
この記事を読んだあなたにおすすめ!
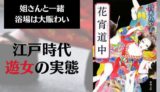 意外と知らない?江戸時代の遊女の実態【姐さんと一緒、浴場は大賑わい】
意外と知らない?江戸時代の遊女の実態【姐さんと一緒、浴場は大賑わい】
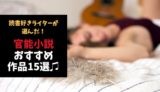
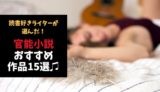
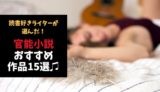



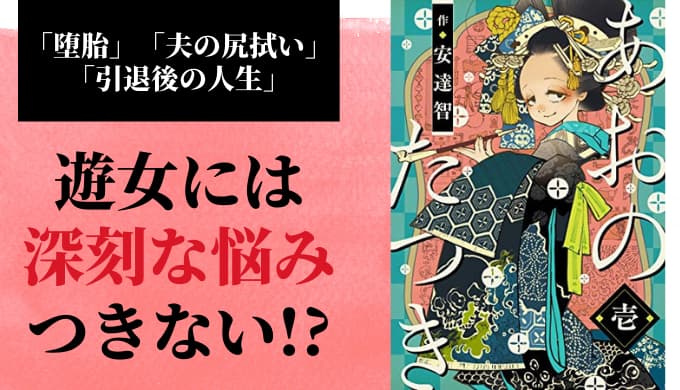
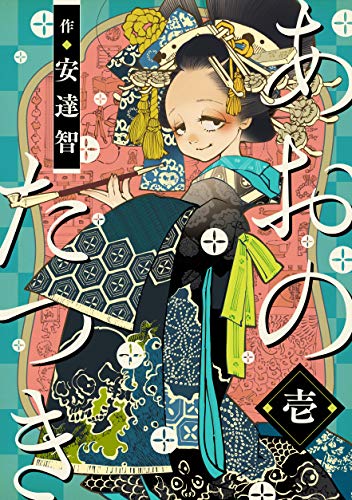
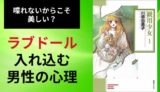

書き手にコメントを届ける