怨ミ晴ラサデオクベキカ。
古今東西、復讐代行を営む必殺仕事人はアンチヒーローとして人気が高い。
ワイヤーやナイフ、あるいは銃で、悪党どもに人誅をくだす彼らはどうして人々に支持されるのだろうか。
今回は京極夏彦『巷説百物語』から、必殺仕事人の魅力を考察していきたい。
魅力その1:常識に縛られない自由人!
本作の主人公、又市とその仲間たちは悪党への制裁を「仕掛け」と称す。
又市たちは一座の所業を妖怪の仕業に見せかける故、巷間では「化け物遣い」とも呼びならわされる。
彼らは依頼さえあればフットワーク軽くどこへでも出かけていく。基本的に旅暮らしだ。
江戸時代の見世物小屋は魔窟だった。
芝居を掛ける芸人もまた、市井の町人とは区別して考えられた。
又市たちは清濁併せ呑むグレーゾーンに生きており、それ故世間の常識や固定観念、道徳に縛られない。
お上が裁けぬ罪に罰を下し、悪党に報いを受けさせるには、彼ら自身がどの勢力にもなびかず属さない、根無し草であるのが大事。
もし家族や恋人、地位や名誉など守るべきものがあれば、又市たちは個人の裁量で動けなくなる。
必殺仕事人の魅力とは自由であること、これに尽きる。
魅力その2:ド派手なパフォーマンスで魅せる!
又市たちは復讐劇を妖怪の仕業に見せかける。
その際はケレンミたっぷりの演出で、悪党どもや目撃者の度肝を抜く。
根回し手回しはしっかりと、細工は流流仕上げを御覧じろ。
ただ悪党を始末して、はいおしまいじゃ面白くない、復讐にもエンターテイメント性は重要だ。
又市たちの仕掛けが鮮やかであればあるほど散り際は語り草となり、「悪党の末路はやっぱりろくなもんじゃないんだなあ……」としみじみする。
標的が胸糞悪いヤツであればあるほど、大掛かりに葬られればスッキリする。
理不尽が腹に据えかねた民衆は、悪党ができるだけ悲惨な末路を辿ることを望む。
必殺仕事人はそのリクエストにこたえ、因果応報のカタルシスをしっかり味わせてくれるのだった。
魅力その3:勧善懲悪の教訓で〆る!悪党への抑止力
又市たちが成した仕掛けは、後世では妖怪の仕業だと信じられている。
真相を知るのは身内を除けば百介くらいのものだ。
「悪いことをしたら罰があたるよ」と吹き込むだけでは弱かろうが、「そんなことをしたら○○みたいに妖怪にとってくわれるよ」と実在の人物名やエピソードを引いて脅せば効果覿面だ。
いやでも説得力が増す。
妖怪を騙って悪をこらしめた話を後世に伝える事によって、再び同じ過ちを犯そうとする人間が出た時に抑止力が働く。
必殺仕事人はその存在自体が悪党にとって脅威。
今まさに道を踏み外そうとしている人間には、「アレの二の舞になりたくない」と改心を促す教訓になる。
故に必殺仕事人は、けっして光のあたらない世直しのヒーローなのである。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 京極夏彦おすすめ小説10選+2【緻密に組み立てられた、京極ワールドの魔力】
京極夏彦おすすめ小説10選+2【緻密に組み立てられた、京極ワールドの魔力】



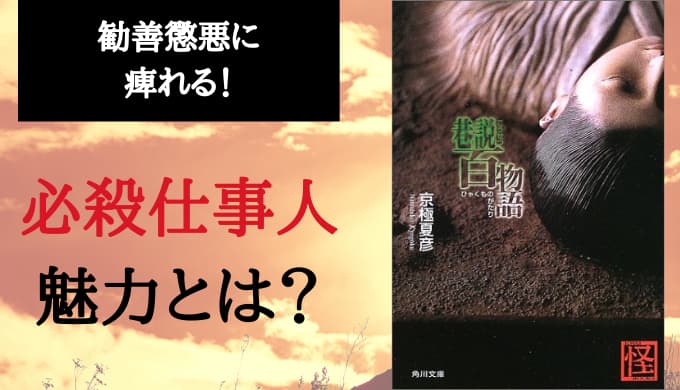
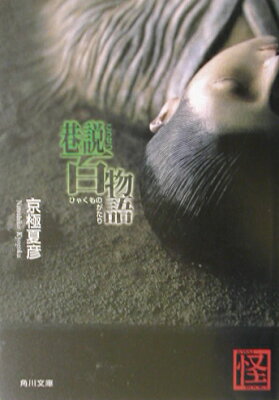
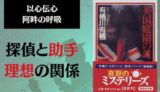
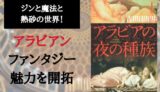
書き手にコメントを届ける