絵画、陶器、演劇、音楽など、「アート(芸術)」と呼ばれる領域を「小説」という形で表現している作家がいる。彼女の名は、原田マハ。
作家デビュー前は、馬里邑美術館(現在は閉館)、伊藤忠商事や森美術館などでキュレーターとして活動しており、その経験が「アート小説」という著者が開拓した分野に盛り込まれている。
アートというと、高尚で近寄りがたく感じる人もいるだろう。しかし、原田マハ氏の小説を読んでいると、アートは日常生活の一部であるかのように、身近に感じられるから不思議である。また、旅好きを公言されているのもあり、旅を題材にした小説やエッセイも発表されている。
今回は数ある原田マハの著書の中でも、おすすめの15冊をランキング形式でご紹介する。
目次
原田マハのプロフィール
1962年、東京生まれ。デビュー作は2005年の『カフーを待ちわびて』(第1回日本ラブストーリー大賞)。その他も受賞歴多数。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞、2016年『暗幕のゲルニカ』でR-40本屋さん大賞、2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞、2018年『異邦人』で第6回京都本大賞を受賞。
1位『本日は、お日柄もよく』
比嘉愛未主演ドラマの原作
「本日は、お日柄もよく」。結婚式のスピーチで使われる文言がついたこの小説は、スピーチを作成する「スピーチライター」に焦点が当てられている。
主人公・二ノ宮こと葉(にのみや ことは)は、出席した結婚式で聞いた久遠久美(くおん くみ)のスピーチに感銘を受け、彼女に弟子入り。スピーチライターの道を目指す。
スピーチライターは、日本ではあまり馴染みがない職業だが、政治家の演説を作成する人というと分かるだろうか。他にも、冠婚葬祭や行事の来賓挨拶を作成しており、意外にも仕事は幅広い。
本書ではスピーチライターの紹介だけでなく、「話す日本語」について分析されている。物語の冒頭は、結婚式の来賓スピーチに眠くなったこと葉がスープに顔を突っ込んでしまう場面から始まるので、肩肘張らず読めるのも魅力だろう。
学校や職場のプレゼンテーションが苦手だという人におすすめしたい。
 『本日は、お日柄もよく』原作小説あらすじと感想【原田マハの人気作!スピーチライターのお仕事小説】
『本日は、お日柄もよく』原作小説あらすじと感想【原田マハの人気作!スピーチライターのお仕事小説】
2位『楽園のカンヴァス』
第25回山本周五郎賞受賞
原田マハの代名詞とも言える「アート小説」はこの作品で誕生した。
舞台はスイス・バーゼル。世界的に有名な絵画コレクター・コンラート・バイラーに招かれた2人の男女、アンリ・ルソー研究者の早川織江(はやかわ おりえ)と、MoMAアシスタント・キュレーターのティム・ブラウンは、バイラーから1枚の絵を見せられる。それは、ルソーの「夢」に酷似した絵「夢を見た」。1週間以内に絵の真贋を正解した者に、絵の取り扱い権利が行くというストーリー。
登場人物が絵画の謎を追っていく様子は、まさにミステリー小説。読み進めるうちに、絵画の真贋について早く先が知りたくなってくる。
アートというと高尚で身構えてしまうが、作中に登場するアンリ・ルソーやピカソは気難しい芸術家ではなく、気さくなパリに住む人間として描かれている。
また、本の表紙がルソーの「夢」なので、芸術に造詣がなくとも読み進められるのも、おすすめする理由だ。
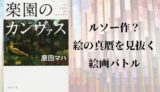
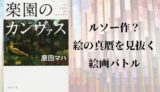
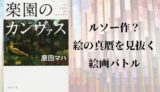
3位『キネマの神様』
沢田研二/菅田将暉主演映画の原作
円山歩(まるやま あゆむ)は左遷を機に、大手デベロッパーを退職。折しも実家の父・円山郷直(まるやま さとなお)が脳梗塞で倒れ、さらにギャンブルと映画につぎ込んだ多額の借金も発覚。
無職になった歩は、父の映画鑑賞ノートを発見し、自分なりの解釈を付け加えたところ、郷直はその文章を映画雑誌「映友」へ投稿してしまう。これをきっかけに歩は映友編集部に採用され、父はゴウというハンドルネームで映画評論ブログを始め、評判を博す。ところが、ブログにローズ・バッドと名乗るアメリカ人から反論が来て…。
ゴウとローズ・バッド、どちらの評論も映画を詳細まで見ていないと書けない内容で、読むだけで映画を見たような気にさせてくれる。
文章もテンポが良く、映画評論が国境や言語の壁を越えて繰り広げられると想像すると、思わずワクワクしてしまう小説だ。
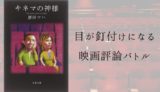
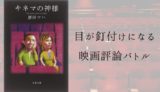
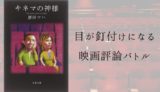
4位『暗幕のゲルニカ』
絵画「ゲルニカ」は、ナチスドイツ軍のスペイン・ゲルニカ空爆による怒りから生まれた。
この「ゲルニカ」をめぐり、異なる時代を生きる2人の視点が交錯する。1人は2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロで夫・イーサンを失った、MoMAキュレーターでピカソ専門家の八神瑤子(やがみ ようこ)。もう1人は「ゲルニカ」制作過程を写真に収めた、ピカソの愛人ドラ・マール。
「人はなぜ戦争をするのか、そして戦争に対し芸術は何ができるのか」という問いを、瑤子とドラの2人を通じて投げかけ、ある一つの答えを導き出す。
戦争という重たいテーマであり、政治的な駆け引きや「ゲルニカ」を狙う存在も登場して一見サスペンスのようだが、本書を通じて戦争と平和を考えるきっかけにもなると思った。
5位『カフーを待ちわびて』
第1回日本ラブストーリー大賞受賞/玉山鉄二主演映画の原作
作家・原田マハのデビュー作。
沖縄の離島・与那喜島(よなきじま)を舞台にした本書は、「嫁に来ないか」と書いた絵馬から恋愛が始まる。その唐突さに反して、島人(しまんちゅぬ)の主人公・友寄明青(ともよせ あきお)と、内地から嫁に来たちゅらさんな幸(さち)との恋愛は、穏やかで純粋だ。
恋愛模様だけでなく、沖縄地方の暖かい穏やかな気候や、古来の風習が生活に根付いている様子、島の密な人間関係も、まるで明青と幸を包むかのように、丁寧に描かれている。また、特徴的な産業がない与那喜島に持ち込まれたハイリゾート建設計画もストーリーにスパイスを与えているだろう。
ストーリー全体から沖縄らしさを感じられる、デビュー作とは思えないほど濃密な小説である。
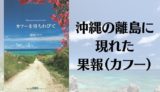
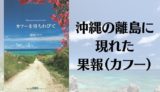
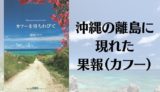
6位『生きるぼくら』
この小説には大きな主題が2つある。「主人公が外の世界へと踏み出すこと」、そして「特殊なお米作り」だ。
母が出ていき、引きこもりの24歳の青年・麻生人生(あそう じんせい)は、途方に暮れていた。母が残した手紙から、別れた父方の祖母・マーサばあちゃんが余命数ヶ月だという手紙を見つけ、彼女が住む蓼科へ1人向かう。
蓼科に着くと、そこにいたのは、認知症で人生を忘れたマーサばあちゃんと別れた父の再婚相手の娘・つぼみだった。家に帰っても誰もいないため、人生は仕方なくそのままマーサばあちゃんの家で暮らすことに。仕事も始め、蓼科での暮らしに慣れてきたころ、マーサばあちゃんから「特殊なお米作り」を聞き、つぼみと挑戦するのだが…。
蓼科で近所の人を巻き込みながら、お米作りに挑戦する様子は、 引きこもっていたとは思えないほど主人公・人生の成長を感じた。
また、「特殊なお米作り」は読んでいるだけで、ご先祖様への感謝の念が募ってくる。
7位『総理の夫』
田中圭×中谷美紀主演映画の原作
20☓☓年の日本で初めて女性の総理大臣が誕生したところから物語は始まる。
新しい総理大臣の名前は相馬凛子(そうま りんこ)。本書は、凛子の夫で徳田野鳥研究所に勤める相馬日和(そうま ひより)が後世の読者のためにと思い、書きだした日記形式で綴られている。
野鳥研究家らしく、人間の行動を野鳥になぞらえて日記の書き出しをしたかと思えば、「総理の夫」となったことによって起きた日常生活の変化、マスコミに追われる日和の苦悩、夫婦の時間が取れずにすれ違う苦難が赤裸々に描かれている。
もし日本で女性総理大臣が誕生したら、起きるだろうと思われる展開が読んでいて面白い。
また、総理の夫となっても日和が一般人の目線を忘れていないので、読者も感情移入がしやすいと思う。
8位『たゆたえども沈まず』
日本人に人気の画家、フィンセント・ファン・ゴッホは、日本の浮世絵から多大な影響を受けたことをご存知だろうか。
代表作の一つ、「ジュリアン・タンギーの肖像」では、何枚もの浮世絵を背景にちりばめて描いている。フィンセントがパリで絵を描いていたのと同時期に、日本人画商・林忠正(はやし ただまさ)は、ヨーロッパで高まるジャポニズム人気に呼応するかのように、パリで浮世絵を販売していた。
実はフィンセントと林忠正は、接点があったという記録はない。本書では、フィンセントの弟テオと、林と一緒に浮世絵を販売していた加納重吉(かのう じゅうきち)を登場させ、フィンセントと林忠正の交流を持たせている。
もし、オランダ人画家のフィンセント・ファン・ゴッホ、そして浮世絵を扱う日本人画商の林忠正が異国のフランス・パリで出会っていたらと想像して読んで欲しい。
これまでと異なる画家フィンセント・ファン・ゴッホ像が見えてくるだろう。
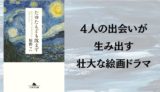
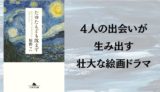
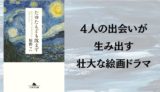
9位『ジヴェルニーの食卓』
第149回直木賞の候補作。
晩年のマチスを家政婦が回想する「うつくしい墓」、亡きエドガー・ドガが残した彫刻を見たメアリー・カサットが回想する「エトワール」、タンギー爺さんの娘がセザンヌに宛てた手紙「タンギー爺さん」、そして元首相クレマンソー来訪のため、モネの義理の娘・ブランシュが迎える準備をする「ジヴェルニーの食卓」の4編が収録されている。
マチス、ドガ、セザンヌ、モネ。この小説では、印象派を代表する巨匠の側にいた女性達の視点で、彼らの苦悩や葛藤、溢れ出すアートへの情熱と繊細な心などが描かれている。
原田マハ氏が本気で巨匠たちと向き合ったという本書。その魅力はなんといっても、気難しいと思われる芸術家たちも実は、市井の人と変わらない日常の営みを送っていると感じられることだと思う。
10位『旅屋おかえり』
アラサーの崖っぷちアイドル・おかえり、こと、丘えりかは、唯一のレギュラー番組だった旅番組「ちょびっ旅」で、スポンサー名を間違えて連呼してしまう。
番組は打ち切られ、次の仕事も全く見つからないおかえりに、「ちょびっ旅」視聴者から依頼がくる。それは、ALSで動くことが難しい娘の代わりに、旅をしてほしいというものだった。
旅行好きの人にとっては、旅代行なんて美味しいと思うかもしれない。しかし、おかえりはただ旅行をするのではない。旅ができない依頼人の思いをくみ取り、まるで依頼人が行ってきたかのように、旅行するのだ。
おかえりが根っからの旅好きだというのが分かるので、読んでいるだけで幸せになれる。また、彼女の打算のないストレートな思いは、依頼者そして周りの人間が心に秘めていたわだかまりをも、雪解けさせてくれる魅力がある。
11位『異邦人(いりびと)』
第6回京都本大賞受賞
篁菜穂(たかむら なほ)は、銀座の一等地に画廊を構える、たかむら画廊の御曹司で専務の一樹(かずき)の妻であり、自身は不動産会社を営む実家が運営する美術館で学芸員をしていたが、東日本大震災発生を機に、放射能の影響が胎児に及ぶことを恐れて、東京から京都へと避難した。
知り合いがほとんどいない京都の画廊で、菜穂は無名作家の絵を見つける。元々美術品の選定眼に定評があった菜穂は、無名作家から才能を感じ取り、その画家へ執着していく。
『楽園のカンヴァス』や『ジヴェルニーの食卓』では、アンリ・ルソーやモネといった芸術家個人に焦点を当てて書かれていたが、本書は芸術そのものに魅入られた人を描いており、他のアート小説とはテイストが異なる。特に、菜穂の芸術家の才能を見極める目と、芸術品を愛するがゆえに見せる執着心には恐ろしさを感じるほどだ。
アート小説の新しい切り口を楽しめる1作。
12位『さいはての彼女』
全4編の短編集。
「さいはての彼女」と「冬空のクレーン」は、順風満帆だった仕事につまずいたキャリアウーマンが、旅先の北の大地での思いがけない温かい出会いによって、硬くなった心が溶けていく物語。
「旅をあきらめた友と、その母への手紙」は、親友ナガラと来るはずだった伊豆旅行に、1人で来ることになったハグこと、波口喜美(はぐち よしみ)の話。
「風を止めないで」は、「さいはての彼女」に登場するハーレーのカスタムビルダー・ナギの母・佐々木道代(ささき みちよ)が応対したナギ宛の不思議な来客の話。
どの物語も主人公は35歳以上の女性で、多少つまづきはあれど、仕事やプライベートをそれなりに充実させている。
そんな彼女たちにもたらされた思いがけない出会いや非日常の世界が、知らないうちに硬く武装してしまった心を溶かしていく感じが読んでいて心地良い。
13位『一分間だけ』
愛らしいラブラドールレトリバーの寝顔が特徴的な本書は、モード誌編集者の主人公・神谷藍(かみや あい)と飼っているラブラドールレトリバーのリラとの物語。
セレブ御用達のペットショップで殺処分寸前だったリラを引き取った藍。しかし、編集の仕事は昼夜問わず働きずくめのため、同棲しているフリーのコピーライターの彼氏・浩介(こうすけ)に平日のお世話を任せ、自分は週末のみ世話をしていた。ところが、浩介との関係に変化が生じ、藍とリラの生活も一変する。
本書を読んでいると、近所の人とペットを通じて交流する様子や、雑誌の校了前で藍がイライラして、自分が引き取ったとはいえ、リラを疎ましく思う様子など、良いことも悪いことも含め、犬を飼ったことがある人には、実感できる描写が多いと思う。
そして、終盤に訪れるクライマックスは、涙を流さずにはいられない。
14位『風神雷神』
夢やロマンがつまった物語。
琳派に多大な影響を与えながら、謎に包まれた安土桃山時代画家・俵屋宗達(たわらや そうたつ)。
宗達の研究者である望月彩(もちづき あや)は、マカオ在住の研究者レイモンド・ウォンより、マカオへ招待された。そこで見せられたものは、天正遣欧少年使節団の一員であり、バテレン追放令でマカオに追放された、原マルティノの書簡と「俵屋宗達」の文字。彩は研究対象である、宗達の壮大な旅に思いを馳せる。
生没年すらはっきりしていないミステリアスな画家ゆえに、展開されるストーリーが壮大。当時の権力者・信長への謁見、ヴァリヤーノとの接触。有馬のセミナリヨでの日々、そして天正遣欧使節団と共に渡欧、イタリアでの出会い。もし俵屋宗達の人生が本書のようだったらと考えると、読んでいて心おどる。
15位『いちまいの絵 生きているうちに見るべき名画』
アート小説家として名を馳せている原田マハが選ぶ、おすすめの26作品が解説付きで紹介されている1冊。
この26枚の絵画は、原田さん自身が衝撃を受けた絵画だけでなく、美術史に革命を起こした絵画も含まれている。
なぜレオナルド・ダヴィンチや印象派画家、ピカソの絵画が当時革新的だったのか、その点も詳しく解説されているので、美術史が苦手な人にもおススメ。
また、『楽園のカンヴァス』や『暗幕のゲルニカ』などに登場した絵画も登場するので、先に作品を読んでいると、より本書が楽しめると思う。
おわりに
原田マハの小説の舞台は多岐に渡っていると思う。
今回挙げた15作品であれば、北は北海道(『さいはての彼女』)から南は沖縄(『カフーを待ちわびて』)まで。
海外にまで広げると、印象派画家たちが活躍したフランス(『ジヴェルニーの食卓』)や、アメリカ(『暗幕のゲルニカ』)。
そして、今回紹介できなかった小説には、上海やイギリスを舞台にした小説もある。
すべての著書に共通している点は、舞台となった場所の空気を感じることだ。
読んでいると、その場に居ないにも関わらず、沖縄やフランスにいるような錯覚を覚えてしまう。
また、特定の土地ではなく、結婚式場(『本日は、お日柄もよく』)や国会議事堂(『総理の夫』)といった空間も同様だ。
もし、この15作品で読みたいと思った本があったなら、「五感を使って読む」ことが楽しめる秘訣。
ぜひ読んでみて欲しい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
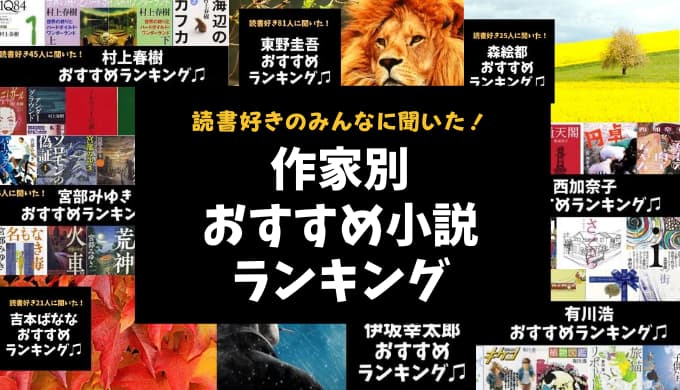





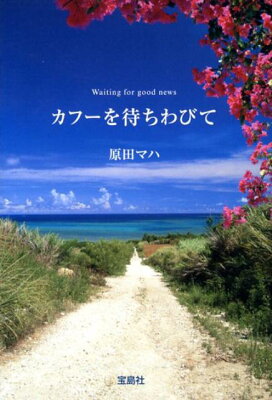


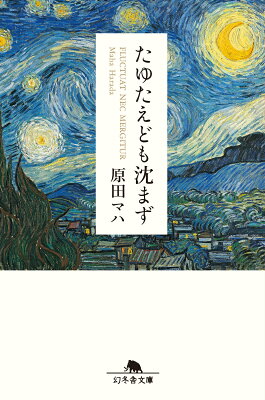








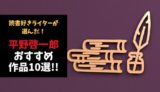
書き手にコメントを届ける