恩田陸の『木曜組曲』は傑作ミステリーだ。
私の好きな恩田陸作品堂々トップでもある。
大作家・重松時子が死んだ木曜日の前後3日間、彼女を偲んで洋館に集まり、飲み食い思い出話に興じる女たち。
メインキャラクターは全員癖が強い物書きであり、創作にかけるその執念と業たるや、読者を圧倒してはばからない。
フィクションとノンフィクション、ライターの存在意義とは…?
『木曜組曲』の舞台となる、うぐいす館を訪れるのは4人の物書きだ。
しかし、そのスタイルはそれぞれ異なっている。
彼女たちの共通点は大御所作家・重松時子に複雑な感情を持っていることだ。
作中、ノンフィクションライターの絵里子が悩みを打ち明ける。
絵里子は長年各分野における著名人を取材し、本を出すのをなりわいにしてきたが、現状に行き詰まって将来に焦りを感じていた。
取材対象が皆クリエイティブな人間であり、セルフプロモーションに意欲的なのも無関係ではない。
対象が自ら言いたいことを発信して読者に届けてしまうなら、ライターの存在意義とは何なのか。
本作の出版当時にも増して、現在の方がよりこのジレンマを身近に感じるかもしれない。
YouTubeやSNSに代表されるように、現代は作り手と受け手の距離がとても近い。
両者はオンラインで活発に交流し、こと表現者に至っては創作活動と広報活動がセットになっている。
そうなると対象をわざわざ取材して本にまとめる意味も失われないか。
他人と細部を擦り合わせる手間や、本になった時に解釈違いが生じる懸念を踏まえれば、自分で好き勝手にやるほうがよっぽどいい。
「嘘がない」「刺激的だ」と、そちらの方を喜ぶファンも大勢いる。
仕事に注ぎこむ時間や労力に比して報われない徒労感が、「このままでいいのか」と絵里子に自問させる。
人の話を書くのではなく、自分の話を書きたい。
自分が作り上げた話を読者に届けたい。
ライターなら誰しも一度は体験したことのある衝動が、絵里子の人生の分岐点となる。
純文学VSエンタメ、内省の深まりと読者の満足感
尚美は主婦層に絶大な支持を得るエンタメ作家。
展開が二転三転する波乱万丈な構成のサスペンスものを多く手がけており、映像化作品も多い。
たとえるなら桐野夏生か。
一方のつかさは純文学作家だ。
彼女のデビュー作は「一日中誰とも口をきかずひたすら患者の歯を削り続ける歯科医の日常」を題材にしており、要約だけで不気味さが伝わってくる。
発足当時から純文学は私小説の側面が強く、エンタメ小説は娯楽性を重視している。
極論付けるなら純文学は作者の方を、エンタメは読者の方を向いているのだ。
前者では作者の内省の深まりが、後者では読者の満足感が評価の軸となる。
本作のラストにおいて、うぐいす館に集った女たちは次に会うときまでに重松時子がテーマの新作を書いてこいと命じられる。
つかさは初めて時子に会いに行った十代の思い出を反芻し、実体験にもとづく個人的エピソードをテーマに選ぶが、尚美は時子モデルの大作家が他人に自作をリライトさせるという、挑戦的なテーマを選ぶ。
ここに物書きとしての二人の違い、めざす方向ならびに着地点の差異が出ていて興味深い。
エッセイストと編集者、静子とえい子の第一歩
静子は時子の妹で大手出版プロダクションの経営者。
美術品や仕事関連のエッセイも手がけており、豊かな教養に裏打ちされたアカデミックな文体が支持を集める。
私の中では「怖い絵」シリーズの中野京子が近い。
えい子は生前の時子と公私ともに親しくしていたベテラン編集者で、うぐいす館の管理を任されている。
兼業エッセイストと編集者。厳密には「小説家」でない。
物書きではあっても、自分で考えた話を書いていたわけではないからだ。
しかし時子の死の真相に一応の答えが出て、静子とえい子の心境は変化する。
静子は姉との確執を振り返り、妹の自分しか知り得ない事実を小説に仕立てたい衝動に駆り立てられる。
えい子もまた一番近くに一番長くいた自分しか知り得ない、大作家の素顔を原稿用紙の升目に落とし込みたくなる。
時子は素晴らしい才能を持った小説家であり、玲瓏と照る月のようなカリスマ性にあふれた彼女の存在は、良くも悪くも周囲に影響を与えていた。
物書きは伝染る。
そばにいると書きたくなる。
どんなに辛く苦しい道のりでも彼女たちが書き続けるのは、自分の中にあるものを吐き出して形にし、自分しか知らない秘密を読者と分かち合い、承認してほしいからかもしれない。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
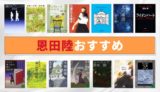 恩田陸おすすめ小説ランキング29選【読書好きが選んだ!】
恩田陸おすすめ小説ランキング29選【読書好きが選んだ!】
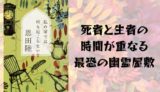
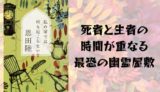
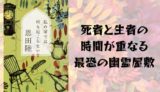



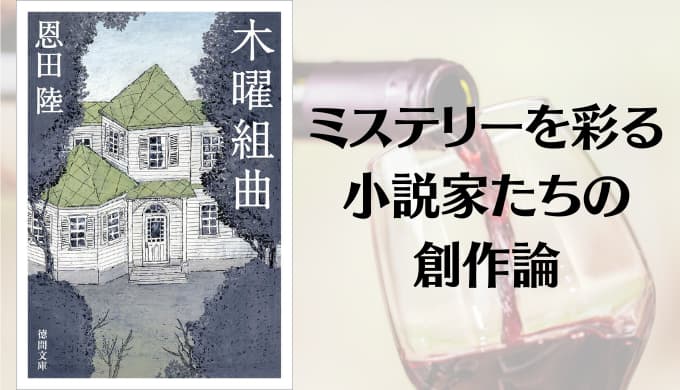



書き手にコメントを届ける