災害や不況、あるいは病気の流行とDV発生件数がリンクしているのをご存知だろうか。
即ち、DVの発生件数は社会不安の増大に比例する。
コロナ禍の今、あなたのまわりにもDVに苦しめられている人がいるかもしれない。
今回はボストン・テランの『音もなく少女は』を参考に、DV被害者の魂が再生していく道のりを考察したい。
家庭の外で理解者を得ること。インターネットも外の世界
本作の主人公イブは聾唖(ろうあ)の少女。
彼女はイタリア系の貧しい家庭に生まれ、犯罪者の父と愛情深い母によって育てられた。
イブの母親であるクラリッサは内気な性格で、横暴な夫にも一切逆らえず虐げられていた。
しかしひょんな事から家の外でフランと出会い、二人は最良の友となる。
DV被害者が家の中に閉じ込められる例は少なくない。
モラハラ夫に行動を束縛され、食糧の買い出しや通院以外外出を許してもらえないというのもよく聞く。
クラリッサは教会の礼拝でフランと出会った。
夫に抑圧されたDV被害者は、家の中だけが自分の居場所だと洗脳されがちだが、世界はもっと広い。
一歩外へ出れば助けてくれる人だっているし、夫の言い分が間違っていると気付かせてもらえる。
クラリッサは教会だったが、場所はどこでもいい。
インターネットだって外の世界に含まれる。
少し検索すればDV被害者の相談を受けているボランティア団体がたくさんヒットするし、匿名で悩みを明かせる掲示板やチャットもある。
そこならばあなたに共感し、親身になってくれる人が必ずいる。
家庭だけが世界じゃないと知り、視野を広げるのも大切だ。
子どもとの相互の愛情を支えに
イブには幼くして死んだ姉がいるが、彼女もまたイブと同じ聾唖だった。
クラリッサは長女の死を嘆き悲しむ。
彼女にとって最大の後悔となったのは、夫が聾学校へやるのを拒んだ為に長女は手話もできず、最後の瞬間に「愛してる」と伝えられなかったことだ。
死にゆく娘に「愛してる」の一言すら伝えられなかったクラリッサはうちのめされ、同じ過ちは絶対しないと決意。
横暴な夫に一歩も引かず、遂にイブの聾学校入りを認めさせる。
子どもを守ろうと立ちはだる母の意志は、DV夫の脅威すら跳ね返すのだ。
固い絆で結ばれたイブとクラリッサのように、子どもと互いにいたわりあえるのならきっと解決策が導き出せる。
あなたは決して一人ぼっちじゃない。
あなたのことが大好きな小さい味方が、一番近くいるのだから。
疑似家族がシェルターとなる。人権を尊重してくれる理解者こそ家族
やがてクラリッサとイブは家を出、フランと3人で暮らし始める。
女性だけ、三位一体の聖家族だ。
戦争の後遺症で子供を産めなくなったフランにすればイブは娘も同然であり、クラリッサとともに無償の愛情を注ぎ、彼女をすこやかに育む。
血の繋がりの有無が家族の条件とは限らない。
血が繋がっていても子供を虐待する親はいるし、一方で他人の子を立派に育て上げる親もいる。
DV夫が支配する機能不全家庭を捨てる英断をしたクラリッサは親友に助けを求め、フランは快く彼女たちを迎え入れる。
どちらの「家庭」の方が居心地いいかは語るまでもない。
父親の怒声や母親の嗚咽を一日中聞かされるほど、子どもにとって耐え難いストレスはない。
脅威からきちんと守ってもらえる場所こそ子どもたちの「家」であり、血の繋がりはなくとも自分たちの人権を尊重してくれる理解者こそ本当の家族なのだ。
友人、上司、ボランティア、ご近所さん……同じDV被害の経験をうけた仲間でもいい。
家庭とは本来安らげる場所である。
信頼し合えるだれかと寄り添い、疑似家族として機能する共同体を作り上げる事で、DV被害者の魂は再生されていくのだ。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
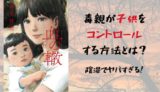 陰湿でヤバすぎる!毒親が子供をコントロールする方法とは?
陰湿でヤバすぎる!毒親が子供をコントロールする方法とは?
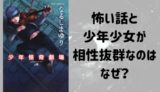
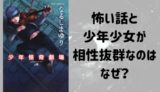
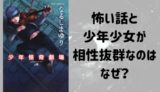





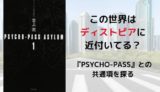
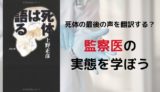
書き手にコメントを届ける