日々痛ましい虐待のニュースが世間を騒がす世の中、自分には何ができたのか考える。
子どもには安心が必要だ。
しかしそれは世界の色んな場所で欠けている。
今回は桜庭一樹『砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない』から、子どもが虐待から生き残る知恵を考察していきたい。
空想が逃げ道となる
転校生の海野藻屑は変わり者だ。
彼女は常に持ち歩いてるペットボトルの水をがぶ飲みし、「僕は人魚なのです」と言い張る、不思議ちゃんで痛い子だ。
そんな藻屑は虐待被害者。
赤ん坊の時に父親に酷く扱われたせいで股関節を痛めて足を引きずり、鼓膜まで破られたせいで耳が不自由だ。
藻屑はスカートの下の打撲の痣を「汚染なんだ」と偽り、自分は人魚でいずれ海に帰るのだから、地上での辛い出来事なんかへっちゃらだとうそぶく。
あまりに頼りない砂糖菓子の弾丸をぽこぽこ世界に撃ち込んで、せめて自分の心だけでも守っているのだった。
もし、本来愛情を注ぎ庇護してくれるはずの親に束縛されて虐待を受けたら、抵抗手段を持たない子どもは現実を否定し、妄想に縋って逃げるしかない。
「自分が悪い子だからおしおきされるんだ」と思い込んで耐える者もいれば、「こんな世界は嘘だ、ほんとじゃない」と暗示をかける者もいるはずだ。
ある種の人間にとって、フィクションは救済装置となりうる。
親の支配下から脱するのが難しい子どもたちは、哀しい空想の中に唯一の逃げ道を求めるのだった。
生活力をつけて自立する。ばっさり切り捨てる勇気
藻屑と対になるキャラクター・なぎさは母子家庭の中学生で、ひきこもりの兄がいる。
なぎさは兄を養うために自立を急ぎ、自衛隊への入隊を志望していた。
虐待する親や機能不全家庭から逃げたければ、一日も早く自立するのが現実的だ。
親元に留まっているから虐待されるのであって、とっとと見限って離れてしまえば手を出しようがない。
中には追いかけて連れ戻しにくる親もいるだろうが、1人でもやっていける生活力を身に付けて守りを固めれば、彼らをサンドバッグのようにうちのめすことも不可能ではない。
本作では虐待加害者と被害者の関係がストックホルム症候群にたとえられているが、一緒にいるからどん詰まりの共依存に陥ってしまうのであり、悪循環に終止符を打ちたいと本心から望むなら、子どもの方から絶縁するに越したことはない。
藻屑は「好きって絶望だよね」と嘆いているが、「ああ、この人どうしようもないな」と思ったらずるずる情けをかけていないで、ばっさり切り捨てる勇気も必要だ。
世界と戦うなら、実弾は効果的だ。
周囲の大人を積極的に利用しろ
本作において、なぎさが最後に頼るのはひきこもりの兄だ。
妹にSOSを求められた兄は何年かぶりに家を出、ストレスで吐きながら山へ行く。
全てが終わってしまったあと、なぎさの担任は生徒を救えなかった自分を責めこう言うのだった。
「だけどなあ海野、お前生きる気があったのかよ……」
本作において担任は存在感が薄く、時々空気が読めない発言をする脇役に過ぎないのだが、この言葉はとても胸に刺さった。
なぎさと藻屑の周囲にはろくな大人がいなかったのかもしれない。
それでも彼女たちが声を上げて泣き付けば、彼らは手遅れになる前に動いてくれたかもしれない。
私たちが頼りないと侮っている大人も一応大人であり、子どもが持ってない知恵や打開策を与えてくれる。
実際妹に頼られた兄は吐きながらも山をめざし、担任は既に動いていたのにと悔し泣きをした。
虐待から生き残りたければ、周囲の大人を積極的に利用してほしい。
虐待ホットラインでも警察でも学校カウンセラーでも近所の人でもなんでもいい。
声を上げれば聞いてくれる人は案外いる。
子どもを助けようと動いてくれる大人はちゃんといるのだ。
すべての大人はかつて子どもであり、砂糖菓子の弾丸ないし実弾で世界と戦ってきた、生き残りの兵士なのだから。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
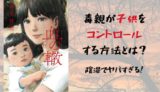 陰湿でヤバすぎる!毒親が子供をコントロールする方法とは?
陰湿でヤバすぎる!毒親が子供をコントロールする方法とは?






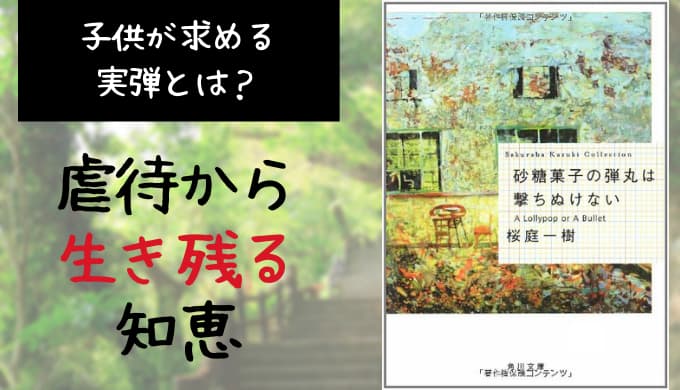

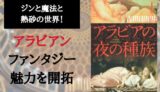
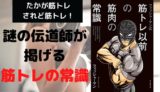
書き手にコメントを届ける